
わずか5人のチームで新たなプリンタを開発?自由なものづくりを実践する開発センターの実像。
Teams
MUTOH ストーリー
武藤工業株式会社 開発センター
LFP開発チーム
MUTOHグループの中核となる武藤工業の開発センターでは、大判インクジェットプリンタなどの総合開発を行っています。総合開発では機構、ソフトウェア、インク、電気、アプリケーションという五つの技術開発グループの担当者がチームを組み、1台のプリンタをつくりあげます。今回は開発センターから5人の技術担当者が集結。武藤工業のユニークなものづくりの魅力を語ってくれました。
武藤工業株式会社 開発センターチーム

機構設計グループ
H. T.

ソフトウェア設計グループ
H. B.

インク設計グループ
T. Y.

電気設計グループ
H. S.

アプリケーション
設計グループ
H. M.
高度な技術を身につけた
人材が武藤工業に集う
― 武藤工業のへの入社理由、入社後の経歴を教えてください
H. T.:大学で機械工学を専攻、研究室では熱流体を研究していました。機械工学はいろいろなことを広く浅く学びます。ここで自らの手で機械を一から設計するものづくりの楽しさに目覚めました。大学は東京だったのですが、やや都会の喧騒に疲れてしまい、就職先は地元の長野で探しました。ものづくりを仕事にしたいという思いから、精密機械メーカーの武藤工業に就職しました。入社してから現在まで機構設計グループでキャリアを積んできました。仕事はプリンタの外観含め、内部で駆動する部品を一つ一つCADを使って図面を起こし、業者に発注して、最終的に工場で組んでもらうまでのプロセスを担当しています。
H. B.:大学は制御工学科、研究室では超音波で金属粉を固めて強度の高い金属をつくっていました。学業の傍ら、趣味でいろいろプログラミングをしていたのですが、徐々に楽しくなり、ソフトウェア開発系の仕事に就きたいと思うようになりました。武藤工業に入社した理由はインターンシップでの経験です。簡単な機械のテストでエラーが出たとき、すぐに社員が飛んできて、サッと解決する姿がかっこいいなと思ったからです。すでに入社してから14年、いろいろな業務に携わりましたが、現在はリーダー業務を兼務しながらも軸はソフトウェア設計グループの業務で、プリンタを動かすファームウェア(プリンタ本体を制御するソフトウェア)などをつくっています。

T. Y.:大学では物質工学を専攻、いまとはまったく違うのですが、反応有機化学の研究室で不斉合成をテーマに、もとは同じ物質でも光学的に構造の違う物質を合成する手法を開発をしていました。武藤工業には、先に就職していた囲碁サークルの先輩の紹介で入社しました。入社後はインク設計グループに所属し、ベンダーに依頼してインクの処方をつくってもらい、それをプリンタに入れて問題のある箇所を指摘して、改良を繰り返して、自社のプリンタにフィットするインクをつくっています。その他、インクの発色に関わるプリンタの動作設計の確認、市場で出たインクの不具合を改善するための解析なども担当しています。

H. S.:大学では電気・電子工学を専攻、基本的な回路の勉強や電気回路の設計、いろいろな実験も経験しました。昔から工作系が得意で、いつか世の中の役に立ち、その活躍が自身の目で確かめられる製品開発の仕事がしたいと思っていました。そんな矢先、武藤工業からのお誘いを受けて説明会に参加。さまざまな生活シーンで活躍する産業用プリンタを見て、電気的に動かす設計がしたいと思い入社しました。現在は電気設計グループで、デバイス動作の評価、回路の設計、つくった回路の安全性の評価などを担当しており、電気とは直接は関係ない部分ですが、図面の設計、ケーブル設計の指示書もつくっています。
H. M.:大学の情報用光学科でパソコンやプログラミングを学びました。卒業研究はAR技術を駆使して、いにしえの諏訪大社を再現しました。武藤工業からスカウトメッセージが来て、説明会を受けたときに入社を決意しました。いずれプログラミングの職業に就きたいと思っていたので、まさに、自分が望んでいたタイミングでした。アプリケーション開発チームに所属し、最初は印刷サンプルを出すところから始めて、色を合わせるプロファイル(色の再現性を調整する設定情報)を作成してモニターと同じ色が出るかの検証を経て、現在は新機能のアプリケーション設計をまかせてもらえるようになりました。つねにお客さま目線で、どうすれば使いやすくなるかを考えながら設計しています。
総合開発では
現場中心でものづくりが進む
― どんな流れで総合開発は進んでいくのですか
H. T.:お客さまからのご要望や市場動向をもとに、経営層が新型プリンタや派生機種(既存モデルをベースに機能や性能を変更した製品)の開発コンセプトを策定します。その後、開発センターに声がかかり、各技術グループから1名ずつメンバーがアサインされ、開発チームが立ち上がります。チームは5人前後の少人数体制で、1台のプリンタをゼロから開発していきます。開発チームには一定の裁量が与えられており、外部からの干渉はほとんどありません。そのため、非常に自由度の高い環境で、エンジニア自身が「つくりたいもの」を存分に形にすることができます。

H. M.:私とH. S.さんは同じ入社3年目ですが、開発チームにアサインされればメンバーの一員です。年齢に関係なく、自分の担当する領域は全面的に任せてもらえますので、かなりやりがいがあると思います。
― 各開発グループで口火を切るのはどこですか
H. B.:機構と電気が最初に動きます。ざっくりとしたハードウェアの構成を決め、それをどう動かすかという段階になったらソフトウェアの出番です。プリンタを動かすファームウェアの動作仕様をつくり込んでいきます。そしてインクとアプリケーションが参加。試作品で色合いや動作の細かい調整を行っていきます。このような順番はあるものの、基本的にチーム全体で進捗は共有します。早い段階で課題や懸念点が出たら解消する必要があるためです。このため、すべてのメンバーは最初から開発現場に立ち会います。
H. S.:当社のプリンタはインクを乾燥させるヒーター機能を搭載しています。たとえば、インク担当から「いままでより今回のインクは乾きにくいからヒーターの性能を上げてほしい」と言われると、機構担当が外にもう一つヒーターをつけられる構造を考え、電気担当が最適なヒーターを選定し、ソフトウェア担当が追加されるヒーターの制御基盤やプログラムをつくり、アプリケーション担当はお客さまがヒーターの温度設定ができるウィンドウを開発するといった感じで、チーム全体が連携しながら進んでいきます。
T. Y.:特殊なインクの利用する場合には、そういうケースが多いですね。ときにはお互いが譲れず議論になるときもありますので、うまく5人で折り合いをつけていくチームワークがなにより重要になりますね。
自身の力、
チームの力でやり遂げる歓び
―どんなときに仕事のやりがいを感じますか
H. T.:機構は一つ一つの部品設計に加えて、本当に組み立てた製品が正しく動くかの動作仕様の評価も行います。新規の機能や部品が搭載される製品の評価はすごく大変です。一発でうまく動作することはまずありません。失敗しては原因を突き止め、次の解決策を考える地道な作業の繰り返しです。チームで相談することも多々あります。ここで苦労するほど、クリアできたときの喜びは大きくなりますね。

H. B.:入社して5年ほど経った頃、新機軸のプリンタ開発に携わったことがあります。私の担当は外部の委託先を取りまとめるファームウェア設計。従来にないタイプの製品で、担当外である機構設計、電気系、インクの知識も必要になり、外部パートナーとの調整や交渉にも苦労しました。この経験を通じて大きな学びとなったのは、プリンタ全体の構造や関係する多くのプレイヤーを意識しながら、ファームウェアを設計できるようになったことです。非常に苦労しましたが、それが自分の成長に繋がったと感じています。
T. Y.:以前、メディアに印刷して出力される最終的な画質をつくるのは誰かという議論になったことがあります。しかし、この部分は、どの担当グループの守備範囲にも当てはまらず、決まった担当者がいませんでした。
そこで、誰かが一歩踏み込む必要があったため、私ともう1人が手を挙げ、必要なイベントを考え、画質をつくり込みました。これを達成できたことが大きな自信になっています。いまではメンバー全員が領域を超えてどんどん踏み込んできます。縦割りの仕事をしていても、良い製品はできてこないことを、みんなが知っているのです。
H. S.:武藤工業では初めてとなるカッティング機能を搭載した製品の開発に携わり、モーターを使って刃を下ろす設計をしたときのことです。細かくカット圧や電流の設定を変え、使う部品や回路の検討で2ヵ月が過ぎていました。そこで初めて細かい設定が決まり、回路の設計が終わり、ようやく思い通りに動いたときは感動しました。自ら新機能を設計して製品に実装された経験は、私の大きな財産になっています。
H. M.:まだ新人で、上司から言われたことをやるしかない時期に、いきなりアプリケーションの新機能をつくる担当に大抜擢されました。わからないことはまわりに教えてもらいながら、どうすれば使いやすくなるかをひたすら考えながら取り組み、満足できる仕上がりになったときの達成感は最高でした。お客さまに使っていただくシーンを思い浮かべて、この仕事をやっていて本当に良かったと思いました。
「One for all, All for one」
の働きやすさがある
―開発センターの環境はどんな雰囲気ですか
H. T.:普段、開発センターのメンバーは基本的に、一つの大きな部屋に机を並べて仕事をしています。仕切りやエリア区分が明確にないため、たとえば、ソフト的でわからないこと、電気的に気になることがあれば、すぐに他部署の先輩、同僚、チームメンバーに相談できます。この風通しのよさが魅力です。一人で悩むことなく、いつでも相談できる中規模の会社ならではの仕事のしやすさがあると感じています。
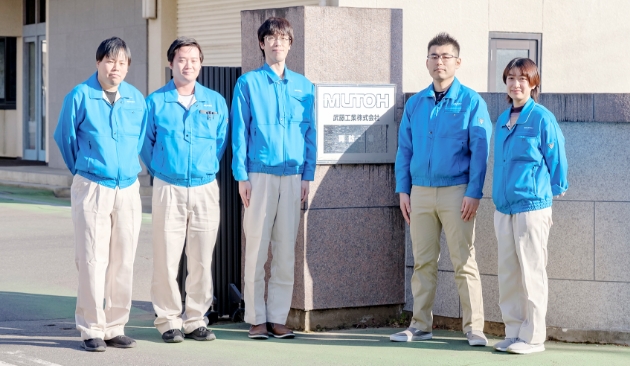
H. B.:開発者、特にソフトウェア担当は、自身の担当領域以外のことについても幅広く理解しておく必要があります。そういう意味では、ワンフロアにさまざまな部署のメンバーがいる風通しの良さは強みになります。仕事をしているだけで、いろいろなものづくりに関する見識が得られ、自身の顔も売ることもできます。かつての私自身がそうであったように、いい人間関係が広がるほど、いい仕事ができるようになるはずです。
T. Y.:ちょっと他部署には聞きづらいことであったとしても、年齢や役職に関係なくみなさん気兼ねなく応じてくれます。加えて、自分の担当領域と他の領域のちょうど境界線で、こういうことを試したいと相談を持ち掛けたり、逆に持ちかけられたりすることで新たな発想が生まれ、プリンタの完成度を高めることもあります。境界のない、あいまいな領域を活用できることは自身の成長にもつながると思います。
H. S.:グループ内での話になるのですが、状況によって一人当たりの仕事量が多い人もいれば、少ない人もいます。このため、手に負えなくなった仕事を、先輩や同僚に頼めば気軽に受け持ってもらえるでしょう。自分では言い出せなくても、上司が気づいてくれます。人間関係がいいので頼りやすいし、逆に頼られることもあります。自由に自分のペースで仕事ができる働きやすい環境だと思いますね。
H. M.:入社時は女性が少なくて不安があったのは事実です。悩みも相談しにくいなと感じていたのですがまったくの取り越し苦労でした。部署間の壁がなく、気さくに話しかけてくれる人が多く、仕事の話だけではなく、ときにはプライベートや趣味の話題で盛り上がることもあります。いろいろな方と話をするうちにどんどん輪が広がり、グループ外でも仲良く話をさせてもらっている顔見知りばかりなので、とても働きやすいです。
―最後に未来の社員に熱いメッセージをお願いします
H. T.:座右の銘は「成せば成る」。自分で動かないと、なにごとも進まないのが仕事です。悩むくらいなら、まずやってみるようにしています。ぜひ、精密機械メーカーに興味がある方は、悩むより先に武藤工業の飛び込んできて欲しいですね。産業用インクジェットプリンタは、小さなインクの液滴を落として絵を描く装置です。インクの落ちる位置が数十マイクロメートルずれるか、ずれないかで、絵が汚くなったり、綺麗になったりします。私の担当する機構だけではなく、電気、ソフトウェア、インク、アプリケーションの高度な連携で数十マイクロメートルの世界を突き詰めているのです。自分の得意領域だけではなく、他部署と協力してプリンタ全体を学びながら仕事をしてみたい人に、武藤工業はぴったりかなと思っています。