

ものづくり全体を見渡せる環境で、
若いうちにしかできない
大きな仕事をやり遂げてほしい。
Leaders & Teams
MUTOHのインパクト
武藤工業株式会社 開発センター長
A. T.
ものづくりの
オールラウンドプレイヤーに
なれる
プリンタは紙に印刷するものだと思われるかもしれません。私たち武藤工業の産業用プリンタは、紙以外のさまざまなものに印刷できる高い付加価値を持っています。たとえば、ビルの壁面や駅のホーム、映画館の入口などで見かける屋外広告、電車やバスのラッピング広告といったものから、キャラクターやアイドルのアクリルキーホルダーやアクリルスタンド、野球やサッカーのユニフォームといった身の回りのものまで、私たちは幅広い印刷ニーズに対応できる大判インクジェットプリンタなどをつくっています。
武藤工業の開発センターは、LFP事業本部の直轄のもと大判インクジェットプリンタの総合開発を行っています。私たちの開発現場は1人あたりの担当できる業務の幅が広いことが魅力の1つだと思っています。プリンタには機構、ソフトウェア、インク、電気、アプリケーションという5つの技術分野がありますが、これらをすり合わせて完成度を高めていくのが総合開発です。たとえ機構担当であってもソフトウェアやインクの知識が必要ですし、要望も出すこともできます。大きな会社の開発部門のような完全分業制ではなく、専門領域以外の業務に関わり、トータルなものづくりの知識、技術を得られるはずです。

10人ほどの少人数体制で1台のプリンタを開発するため、自分の意見が製品に反映されやすいこともポイントです。もちろん、営業や企画からの要望もありますが、細かいところまで指定されるわけではないため、想いを込めた機能や技術がお客さまに届いてることを実感しやすいと思います。製品のサポートもやっていますので、お客さまを訪問して、声を直接聞いて、改善する業務もあります。つまり、企画からメンテナンスまで、ものづくりのPDCAサイクルにしっかり関われる環境が開発センターにはあるのです。
私は武藤工業で働く1人ひとりに経営者の意識を持って欲しいと考えています。いろいろなことに関心を持ち、首を突っ込み、少数精鋭の組織を活性化するために、なにをすべきか、なにができるのかを自分の専門領域にとらわれず、柔軟に考えられるそんな方を武藤工業の開発センターは求めています。
開発のトップとして
社員の意識変革に取り組む
私は子供の頃からものづくり、機械いじりが好きで、よくプラモデルやラジコンなどを組み立てて遊んでいました。愛読書は「子供の科学」、この頃から将来はものづくりの仕事に就くことを漠然とイメージしていたのかもしれません。中学卒業後、高専に進学し、電気情報システムを専攻。卒業後は医療系の会社に就職、技術営業兼ルートサービスの仕事をしていました。ここで学んだお客さまの応対スキルは現在の業務でも非常に役立っています。2年ほど働いたところで、武藤工業と同業の産業用プリンタメーカーに転職し、開発に従事することになります。
当時は武藤工業を強くライバル視していました。
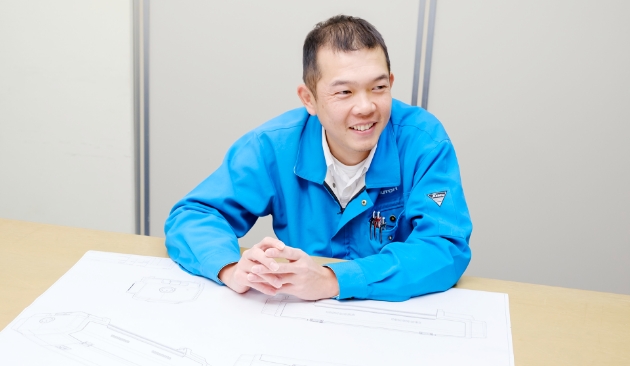
そこからは、ずっと開発畑を歩きまして、30歳を過ぎた頃には開発部門のトップに昇り詰めました。ここでふと、その先のキャリアがないことに気づいたのです。経営者の意識を持って働くことは重要ですが、自分自身が経営者になるつもりは毛頭ありませんでした。ものづくりの現場に身を置く技術者であり続けたかったのです。ほぼ技術者としてやるべきことは達成できた状態で、このまま残り30年近く同じポジションで働き続けるイメージが湧かなかったため、新たなチャレンジの舞台を求めて転職を決意。その後、車載部品メーカー勤務を経て、かつてのライバル会社だった武藤工業に入社します。
最初の1年半くらいはアドバイザーのような立場でしたが、それ以降は開発の責任者として組織運営に携わっています。開発のトップとして最初に取り組んだことは社員の意識変革です。長年、OEMなどの受託業務が多く手がけてきた影響で、当時は良くも悪くも自分を出さない受け身の社員が大多数でした。私を介さないとお客さまとのやりとり、開発の判断もできない状況を変えるために、まず予算の権限を現場に渡しました。予算内であれば自由にやっていいルールをつくったのです。
さすがに野放しにはできないので、要所のプロセスでは目を通しますが、それ以外はいっさい口を出さないようにしたのです。要求されていることを理解、目標を設定して、日程と仕様を決め、きちんと結果を出してくれれば手段は問わないと伝えました。この開発現場への権限委譲により、社員の意識は徐々に変わっていきます。現在は開発のプロジェクトリーダーが自身の判断で仕様を決め、お客さまやチームと議論した上で設計を詰めるようになりました。のびのびと働ける喜びを社員たちも感じていると思います。
いましかできない仕事に
挑んでほしい
変化が激しく先行きが見えにくいVUCAの時代を乗り切るためにはスピーディな意思決定と行動が必要になります。そのためには、ますマーケットニーズの変化を敏感に察知する力が不可欠です。開発者にはどんどん外に出てお客さまと対話し、展示会やイベントにも積極的に足を運び、業務に活かせる情報を取り入れてほしい。

その上で個人への権限移譲を進め、開発のスピードを上げていくことが直近のミッションです。小さい単位でものを動かし、開発のサイクルを早めて、お客さまのニーズにタイムリーかつ的確にレスポンスできる開発体制を築いていきたいですね。
社員の自発性を促すために業務改善の取り組みも進めています。業務改善のテーマを自由に決めて、一緒にやりたい仲間を募ってチームを編成、1年間かけて取り組みます。必要な経費は会社の負担、優秀な業務改善を遂行したチームには賞金も出ます。中間報告には管理職が立ち合いますが、いっさい活動には口を出さないルールです。毎年、開発センターでは期首方針を出すのですが、今年の方針は「仕組みをつくる」「人材育成」です。技術継承のためにはデータ化が必要など、この方針に沿った業務改善のテーマが出てくることが多いですね。そういう思考が根付いてきたのはいい傾向だと思っています。
自身の専門性を活かしてキャリアアップできることは、これから働く企業を選ぶ際の重要な指標の1つです。武藤工業には専門性を突き詰められる成長、挑戦の機会が多くありますし、オールラウンドプレイヤーとして活躍できる環境もあります。ものをつくり上げるプロセス、ことを進めていくプロセス、さまざまな人と協業するプロセスなど経験し、トータルなものづくりの仕事を勉強できると思います。個人に権限を与えますので、自分の想いを込めた自由なものづくりもできます。小さい組織でPDCAサイクルをスピーディに回す経験は、ものづくりを俯瞰し、自らの手で大きな仕事をこなせる力につながります。
おそらく、この力はこれから先、技術者として成長し続けるための、大きな武器になるはずです。
私が技術者として大事にしている座右の銘は上杉鷹山の「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。この後半のところが重要で、ただ待つだけで行動しなければ、いい結果には結びつくことはありません。とくに若い人には、いましかできない仕事を積極的にやりなさいと話すようにしています。多少の無理や苦労はあってもいい。必ず成長の糧になるからです。私のように家庭を持ち、子供ができたら、なかなかできる機会も減ってくるので、身軽で元気な若いうちに仕事で思い切ったチャレンジをしてほしいですね。挑戦を支えてくれる仲間がいます。失敗を咎めず、成功を評価する体制もあります。そんな武藤工業の開発センターで、オールラウンドプレイヤーの技術者を目指してみませんか。
OFF TIME
私は単身赴任なので、平日は帰宅してテレビを見ながらお酒を飲むのが日課です。休日は家に戻り、妻、中学生の娘、小学生の息子と一家だんらんの時間を過ごしています。子供たちが野球をやっているので試合を観戦したり、キャッチボールの相手をしたり、休日の方が疲れますね。それでも、私にとっていましかできないことは子供と一緒に過ごすこと。あと数年はこの時間を大事にしたいと思っています。